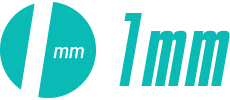難波拓未/ABEMA
「わからないことだらけ」のサッカーに誠心誠意で──。素顔を引き出す西澤由夏アナウンサーのインタビュー術|「サッカーと言えば、ABEMA」への挑戦

Writer / 難波拓未
留まることを知らない活躍ぶりだ。「ABEMA」で放送中のバラエティー番組『チャンス時間』でお馴染みの西澤由夏アナウンサーが、2023年7月『ABEMAスポーツタイム』放送開始を契機にサッカー報道の最前線にも進出した。新しく担当ジャンルに加わったサッカーとは、どう向き合っているのか。そして選手の素顔を引き出すインタビューの秘訣とは。
(取材日:9月10日)
番組収録後、プロデューサーに質問攻め

──現在は『ABEMAスポーツタイム』の進行や番組内での選手インタビューなど、「ABEMA」のスポーツ報道でも活躍されていますが、もともとサッカーとの接点はありましたか?
全くと言っていいほど接点はなかったです。小さい頃からテレビを見ることが好きでしたけど、サッカー中継を見ることはなかったですね。ただ、スポーツに無関心というわけではなく、小学生で陸上、中学生でバスケ、高校ではダンスをやってきて、スポーツは“する”ことのほうが多かったと思います。もちろん最近はサッカーをはじめ、いろいろなスポーツを見ますけど、学生時代はそこまで触れてこなかったんですよね。
──サッカーに触れるキッカケは「ABEMA」でのお仕事だったのですね。
最初のお仕事は、FC町田ゼルビアの応援番組『FC町田ゼルビアをつくろう〜ゼルつく〜』にスポット出演させていただいた時で、本格参入は『ABEMAスポーツタイム』からになります。
──サッカーと関わり始めた頃、どんな印象を持ちましたか?
やっぱり難しかったです。取材すればするほど、勉強すればするほど疑問点が生まれて難しくて。ただ単に見ているだけではわからないことがたくさんあると感じました。その難しさは今も感じていて……、本当に勉強中の身です。
──どのように勉強しているのですか?
とにかくわからないことだらけなので、わからないことをひたすら聞くことを徹底しています。見る、聞くの繰り返しです。
「聞く」に関しては、ありがたいことに「ABEMA」のサッカー番組や中継の制作陣に詳しい方がたくさんいるので、『ABEMAスポーツタイム』の生放送が終わった22時半過ぎから「ちょっと時間ください!」と言って、わからないことを「ここって、どういう意味ですか?」と全部聞いています。スタジオの閉館時間ギリギリまで教えてもらうことも多く、「もう閉めるので帰ってください」と追い出されることも日常茶飯事です(笑)。
帰宅後も深夜に関わらずプロデューサーやディレクターに電話に付き合っていただき、何時間もひたすら質問して理解していくことを手伝ってもらっています。疑問をすぐに解消できる環境には本当に感謝してもしきれません。
──サッカーを勉強していくことで感じたこと、知った魅力などがあれば教えてください。
中継の見方が変わって、楽しさが増しました。今までだったらボールを持っている人だけを何も知らずに追っていたんですけど、オフ・ザ・ボールの大切さやビルドアップなどの戦術的な動き方を勉強して、知れば知るほどサッカーの試合を見ることが楽しくなりました。解消したい疑問点も増えて、どんどん面白さを感じています。
踏み込まれたくない領域を察知する

──『ABEMAスポーツタイム』で日本代表選手にインタビューされていますが、その時に使用する資料は自分で用意しているのですか?
資料には2種類あります。1つは、ざっくりとした構成や流れが書いてあるインタビュー案です。ディレクターさんから事前にいただき、それを確認しながら自分で質問を追加し、疑問点をメモしていき、質問シートを作成します。
もう1つは自作の自分専用資料です。選手のプロフィールはもちろん、海外で活躍されている選手であれば、所属する海外チームでのニュースをチェックしたり、過去に出演している動画を見たりして、その内容を文字に起こしながらシーズンをイチから振り返って情報を整理しています。
──印象に残っているインタビューはありますか?
『ABEMAスポーツタイム』で最初にインタビューした、日本代表DFの板倉滉選手(ボルシア・メンヒェングラートバッハ/ドイツ1部)ですね。私はサイバーエージェント入社2年目まで『アメーバオフィシャルブログ』の営業を担当して、3年目からアナウンサーをさせてもらっているんですけど、板倉選手とは営業時代につながりがあって。当時、川崎フロンターレの選手としてブログ開設を担当したのが私だったんです。
──インタビューはどれくらいオープンに話してくれるかという部分が選手によって違うなか、どこまで想像して準備しているのでしょうか?
その選手のテンション感や雰囲気は過去の映像を見ているだけではわからない部分があるので、もう出たとこ勝負ではあるんです。ただ、インタビューが始まる前のアイスブレイクは心がけています。それぞれの選手に合わせたお話をするようにしつつ、絶対に堅苦しい話はしません。身長の話や、「ABEMA」を見てくださっている方であれば番組の話など、日常会話をすることによってリラックスできると思うので、欠かさずやっていますね。
──インタビューでは専門的な話だけではなく、選手のパーソナリティも引き出されています。特に長谷川唯選手に冨安健洋選手との関係性を聞いた場面は印象的でした。
その場の温度感を気にしつつ、もともと用意していた質問でした。ただ、実際に聞くかどうかはすごく迷っていたんです。プライベートに突っ込んだ質問をすることで、そこまで築いてきた関係性が崩れるかもしれないし、この先に聞きたいことも聞けなくなってしまうかもしれないという不安があったんですけど、思い切って聞いてみました。
──カフェでお話を聞いていましたが、そのロケーションも手伝って?
正直カフェに入ってからも迷っていたんですけど、聞くならここだと思って聞きました。長谷川選手の返しが秀逸だったからこそ、助かった部分もあったんですけどね(苦笑)。
──西澤アナウンサーだからこそ引き出せた答えだったと思います。
初対面の方にインタビューすることが多いので、現場に入ってから空気づくりはかなり意識しています。その方が嫌がるところには踏み込みたくはないですし、踏み込み度合いはプライベートでも気にしていますね。例えば友だちとのコミュニケーションにおいて、どれだけ仲が良くても入り込まれたくない部分があるじゃないですか。普段からそういうところを読み取って過ごしているので、それが取材に生きているのかなと思います。
──相手の“不可侵領域”を適切に察知する感覚は、もともと持っていたのですか?
営業職の時に鍛えられたのかもしれません。営業のお仕事は初対面の方とお話をすることばかりで、そのなかで嫌がられることをわかっていながらも提案をしなきゃいけない部分がある。そこのさじ加減は営業職のトークで学んだのかなと思っています。だからプライベートで友だちにも、取材で選手にも同じようにできるんですけど、これが 彼氏になると全くできないんですよ(苦笑)。
スポーツに興味を持ってもらい業界全体が盛り上がる“エントリーメディア”を目指して

──現在サッカー報道は映像での伝え方が主流になりつつあったり、話題の中心がSNSに移ったりするなど変化していますが、伝え方や届け方などを意識していたりしますか?
他のアナウンサーや他のメディアが聞かないポイントや、「ABEMA」だから聞けることは試合を見ながら考えてピックアップするようにはしています。実際に選手に聞いたことが話題になったり、記事にしてもらってPV数が伸びたりしたこともあったので、最近はより多くの人に関心をもってもらうことへの挑戦はしていますね。
──「ABEMA」は2022年カタールワールドカップやEURO2024を全試合無料放送してきて、サッカー報道においていろいろな試みを積極的にしていると思いますが、どのように感じていますか?
手前味噌ではありますけど、社内にいながら毎回スピード感がすごいなと。本当にそのスピードに付いていくことに必死と言いますか。大きなプロジェクトに向かう行動力と、決まってからのスピード感が本当にとてつもなくて……。
例えば、EURO2024の放送が正式決定したのが開幕直前前で、決まった直後に長谷部誠さんを解説にアサインしています。そして、たまたまその時期は広島で行われた日本代表の試合に取材に行っていたんですけど、一緒だったディレクターさんが横で「EURO決まった。2日後にドイツに行ってきます」と言い出して、「えっ、ドイツってそういう感じで行くんだっけ!?」みたいな。会社の中にいるからこそ、スピード感のすごさをより肌で感じていますし、そこが「ABEMA」らしさかなと思います。
──スポーツ中継が有料化していく流れのなかで、ワールドカップとEUROの無料放送は大きなインパクトがありましたし、「ABEMA」としては『ABEMAスポーツタイム』も含めて間口を広げる取り組みをされていますが、それが届いている実感はありますか?
届いている実感は、ワールドカップの時に最も感じましたね。今まで「ABEMA」を見ていなかった人も、知らなかった人も、それをきっかけに「ABEMA」を見始めたという声を聞きました。
スポーツエンタメ局からは「エントリーメディアでありたい」ということを共有されているんです。「ABEMA」が無料でスポーツ中継をしたり、インタビュー内容をYouTubeなどで開放することによって、そのスポーツに興味を持ってもらい業界全体が盛り上がる。そのキッカケになりたいという思いから、“エントリーメディア”を掲げて活動しています。
ただ、たった1年でわれわれメディアのできることも、できないことも変わっているじゃないですか。なので正直、半年後のこともわからないと思っています。それでも「『ABEMA』のサッカーって、ずっと尖ったことをやっているよね。面白いことをやり続けているよね」と言われ続けるメディアでありたいですし、そこを目指していきたいです。「ABEMA」はその軸をぶらさず、起きていることに対してコミットし続けてきたと思うので、引き続きやっていきたいです。